冷蔵庫を選ぶとき、「容量」「サイズ」「デザイン」「静音性」など、気になるポイントがたくさんありますよね。特に一人暮らしや二人暮らしを始めるタイミングでは、初めて冷蔵庫を買う方も多く、「無理なく使える」「生活にフィットする」モデルを選びたいものです。そんな中で注目したいのが、三菱のPシリーズ。今回はその中でも「[三菱MR‑P17M]」と「[三菱MR‑P15M]」という2モデルを、やさしい口調で初心者にも分かりやすく比較していきます。この記事を読めば、どちらを選べば自分の暮らしに合っているか、きっとスッキリ見えてきますよ。
はじめに
三菱冷蔵庫Pシリーズが人気の理由
Pシリーズが人気の理由は、コンパクトながら使いやすい工夫がたくさん詰まっていることです。たとえば、「幅480mm」というスリム設計で、置き場所に余裕がない部屋にも入りやすいこと。実際に、MR‑P15Mでは「幅480×奥行595×高さ1,213mm」というスペックが公式に記載されています。また、静音約22dBという静かさもポイントで、夜に寝室と近い位置に置く場合でも安心な設計です。さらに「ドア素材が鋼板」「間冷式(ファン式)冷却方式」「ノンフロン冷媒使用」など、環境にも配慮されています。
この記事でわかること(比較のポイント)
この記事では、主に次のポイントをわかりやすく比較します:
- 容量・サイズなど数値的な違い
- 使い勝手・機能性の違い
- 価格・コストパフォーマンスの違い
- 実際の口コミ・レビューから見える満足点・注意点
- どんな人にはどちらのモデルが向いているか
これらを整理して、「自分にぴったりの1台」を選ぶお手伝いをします。
どんな人におすすめ?(一人暮らし・二人暮らし・省エネ重視)
- 軽く自炊する「一人暮らし」には、あまり大きすぎない容量で静かな冷蔵庫が嬉しいですよね。
- 二人暮らしやまとめ買い派の方には、容量や高さが少し余裕のあるモデルが安心です。
- そして「電気代・省エネ性能を重視したい」なら、年間消費電力量や運転音も要チェックです。
今回比較する2モデルは、こうしたニーズに応じて選び分けられる候補となっていますので、自分の暮らしスタイルに合う方を見つけてみましょう。
三菱冷蔵庫Pシリーズの基本情報
Pシリーズとは?特徴とラインナップ
Pシリーズは、三菱電機の冷蔵庫ラインの中でも「コンパクトかつ日常使いにちょうどいい」モデル群として位置付けられています。例えば幅が480mmと、一般的な“幅600mm級”よりスリムな設計により、限られたスペースでも設置しやすいのが魅力です。スペック表からも、MR‑P15Mで「幅480×奥行595×高さ1,213mm」という記載があります。また、共通仕様として「2ドア」「右開き」「間冷式(ファン式)」「鋼板ドア」「耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル」などがあげられています。こうした“日常をちょっとラクにする工夫”が散りばめられていて、幅広い暮らしにマッチするシリーズと言えます。
MR‑P17Mのスペックと主な特徴
「MR‑P17M」は、定格内容積168L、幅480×奥行595×高さ1,338mmというサイズで、年間消費電力量304kWh、静音約22dBという仕様が公式に確認できます。ドア色はマットサンドブラック/マットホワイトが用意されており、デザイン賞(グッドデザイン賞)を受賞していることも紹介されています。冷蔵室に低温ケース9Lを備えていたり、3段ガラスシェルフといった使いやすさの工夫も入っています。
MR‑P15Mの概要と基本性能
一方「MR‑P15M」は、定格内容積146L、幅480×奥行595×高さ1,213mmという少しコンパクトな設計。年間消費電力量300kWh、静音約22dBという仕様も公式に確認されています。簡単に言えば、「少し小さめサイズで、必要最低限の使いやすさを備えたモデル」という印象です。冷蔵室も100L(うち低温ケース9L)という表記もあり、使い勝手としては日常の食材管理に十分な仕様と言えそうです。
Pシリーズ共通の魅力:静音性・デザイン・省エネ性
両モデルに共通して言える魅力として、まず静音性があります。どちらも「静音約22dB」という記載があり、賃貸やワンルーム・寝室近くでも気になりにくい静かさが魅力です。また、デザイン面ではマット仕上げのカラー(マットサンドブラック・マットホワイト)が選べ、フラットトップテーブル(耐熱約100℃)が採用されているため、キッチンに併設してもすっきり、上部を作業台・家電置きスペースとして使うこともできます。省エネ性についても、「2021年度省エネ基準達成率101%」という記載があり、一般的な家庭でも安心して使える設計です。
旧モデルとの違いと改良ポイント
Pシリーズの新モデルとして、最新の「MR‑P17M/MR‑P15M」では、以前のモデルに比べて「使いやすさ」「メンテナンス性(棚が外して洗える)」「2Lペットボトル3本収納可」などの機能が充実しています。例えば公式仕様では、「棚が外して洗える」や「ヨコ取りポケット」「ドアポケット大容量」「ボトルストッパー」などの記載があります。こうしたポイントは、毎日の使い勝手を上げる上で嬉しい改良と言えます。


MR‑P17MとMR‑P15Mの違いを徹底比較
容量とサイズの違い(生活スタイル別おすすめ)
まず、容量とサイズから比較します。
- MR‑P17M:定格内容積168L、冷蔵室容量122L(うち低温ケース9L)、型寸法 幅480×高さ1,338×奥行595mm、質量37kg。
- MR‑P15M:定格内容積146L、冷蔵室容量100L(うち低温ケース9L)、型寸法 幅480×高さ1,213×奥行595mm、質量35kg。
この違いを暮らし視点で見ると、例えば「二人暮らし・まとめ買い派」ならMR‑P17Mの方が容量に余裕があります。一方「一人暮らし・自炊少なめ」「キッチンが狭め」なら、MR‑P15Mの高さ(1,213 mm)が低めなので、設置スペースが限られる場合に有利です。価格もMR‑P17Mの方が若干高めであるため(例:70,642円~ vs 60,348円~)コスト面でも差があります。
冷凍室の構造と収納力の違い
両モデルとも冷凍室46L(うち33L)と同じ容量が記載されていますが、それ以外の冷蔵室構成・ドアポケット構成などで利用感に違いが出る可能性があります。共通仕様として「3段ガラスシェルフ」「2Lペットボトル3本収納可」「ドアポケット大容量」「タマゴトレイ」「チューブスタンド」などが採用されています。ただし背の高さが異なるため、冷蔵室の“上段からの見下ろし”や“奥行き感”など設置環境での使いやすさには差が出るかもしれません。「まとめ買い→高さがあって取り出しにくい」などの点も考慮すると良いでしょう。
省エネ性能・年間電気代の比較
年間消費電力量で比較すると、MR‑P17Mは304kWh/年、MR‑P15Mは300kWh/年という数値が公式に記されています。ほぼ差は小さいですが、容量が大きいモデルの方が若干電力消費が上、という構図です。長く使うことを考えると、この差が積み重なっていく可能性があります。ただし、家庭の利用頻度・設定温度・設置環境(冷蔵庫の裏側の放熱スペースなど)によって実際の電気代は変わるので、「たった4kWh/年」の差だからと言って過信せず、自分の生活スタイルを軸に選ぶのが良いでしょう。
静音性・運転音の実測データ
どちらも「静音約22dB」という記載が公式にあり、夜間にキッチン隣やリビング兼寝室でも“気にならない静かさ”が期待できます。購入後のレビューでは、「音が小さくて安心」という声が多いため、静音を重視する方にはどちらも魅力的。ただし、冷蔵庫の振動・設置時の床の状態・隣接家具との距離などによって体感は変わります。設置時には「床が水平か」「背面に空間はあるか」も確認すると、より静かに使いやすくなります。
デザインとカラーの違い
カラー展開は両モデルとも「マットサンドブラック」「マットホワイト」となっており、部屋の雰囲気に合わせて選べるデザインです。また、Pシリーズ共通のフラットトップテーブル(耐熱約100℃)が採用されており、キッチン家電や食品を置く“セカンドテーブル”として使いやすい点も魅力。高さの違い(1,338mmと1,213mm)によって、部屋の景観・腰の高さでの操作感が変わるため、見た目と使いやすさどちらも考えて選ぶと安心です。
開閉方向と設置スペースの違い
ドアの開き方(右開き)・ドア数(2ドア)は両モデル共通です。設置時に特に注意したいのは“高さ”と“上の収納とのクリアランス”です。MR‑P17Mは高さ1,338mmなので、吊り戸棚や上部に収納があるキッチンでは開閉の邪魔にならないか、また搬入時にドア幅・天井高のチェックが必要です。MR‑P15Mの高さ1,213mmなら「少し余裕があって設置しやすい」可能性が高く、引っ越しや狭いキッチンでも安心です。加えて、背面や側面の放熱スペース(取扱説明書では据付スペース要確認)も忘れず確認しましょう。
★比較表
| モデル | 定格内容積 | 冷蔵室容量 | 外寸(幅×高さ×奥行) | 質量 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MR‑P17M | 168L | 122L(うち低温ケース9L) | 480×1,338×595mm | 37kg | 304kWh/年 |
| MR‑P15M | 146L | 100L(うち低温ケース9L) | 480×1,213×595mm | 35kg | 300kWh/年 |
使い勝手・機能性の比較
収納レイアウトと棚の使いやすさ
どちらのモデルも、ガラスシェルフが全段に採用されており、棚が外して洗える構造になっています。ドアポケットには2Lペットボトルを3本収納できるスペースがあり、ドアポケット自体にボトルストッパー付きという工夫も。特に日常で“飲み物を冷やしたい・すぐ取り出したい”という場面では、このドアポケットの使いやすさがヒットします。収納レイアウトでは、冷蔵室内が広めなMR‑P17Mは「大きめ食材を入れたい」「まとめ買いした冷蔵品を並べたい」という方に向いています。逆に、MR‑P15Mは高さ1,213mmということで、腰の位置から上がスムーズに見渡せて「少人数・自炊中心」の暮らしにマッチしやすいです。
製氷機能・霜取り性能の違い
両モデルとも「ファン式自動霜取り」が搭載されており、霜取りの手間がかからない設計です。製氷機能の詳細な仕様(製氷スペースの形状・取り出し易さ)については公開スペックが少ないですが、冷凍室・冷蔵室共に使いやすさが追求されているシリーズなので、日常使いでは大きな差を感じる可能性は低いです。とはいえ、「氷をよく使う」「冷凍食品を大量にストックする」という用途では、庫内の奥行き・冷凍室サイズ・扉開けた時の見通しなどを実店舗で確かめると安心です。
庫内照明・操作パネルの工夫
庫内LED照明が両モデルで採用されており、夜間や暗めのキッチンでも庫内が明るく見やすくなっています。また、棚やドアポケットの位置調整が可能な構造(チェンジポケットやタマゴトレイなど)も搭載されており、使い方に応じて「どこに何を入れるか」「高さをどう調整するか」が柔軟にできる点が便利です。特に冷蔵庫初心者の方には、「定位置が決まる」と食材管理がラクになっておすすめです。
実際の使用感と日常の利便性
実際の口コミでは、「高さが低めで使いやすい」「ドアを開けても音が気にならない」「飲み物を出し入れしやすいドアポケットが良い」といった声が目立っています。容量・サイズ・設置場所のバランスが合っていれば、「買ってよかった」「日常使いがラクになった」と感じることが多いようです。一方で、「上段が少し奥にあって見えづらい」「背の高い人には少し低めかも」という意見もあるため、身長・習慣・家族構成などを併せて「自分に合う高さか」を確認することがおすすめです。


口コミ・レビュー分析
MR‑P17Mの口コミまとめ(満足点・不満点)
満足点としては、「容量に余裕がある」「見た目がスタイリッシュ」「静音性が高い」という声があります。まとめ買いや冷蔵食品のストックをしたい家庭には好評です。逆に不満点としては、「高さが少し高めで子どもや腰の低い方には上部が使いにくい」「設置場所によっては搬入が少し大変」という声もあります。購入前に設置スペース高さやキッチン収納の位置を確認するのが安心です。
MR‑P15Mのレビュー傾向(静音性・使いやすさ)
こちらは「コンパクトなサイズでキッチンになじむ」「静かで使いやすい」「設置スペースが限られていても安心」という声が多いです。特に一人暮らし・自炊中心の方には「これで十分」という満足度の高さが伺えます。一方で「もう少し容量があれば」「冷蔵室内の高さが少し物足りない」といったレビューもあり、暮らしのスタイルが少し変わると“あと少し余裕があれば”と思う場面も出てくるかもしれません。
両モデルの比較:どちらが満足度が高い?
総じて言うと、「用途・設置スペース・人数」に合ったモデルを選べば、どちらも満足度は高いです。
- 一人暮らし/キッチンが狭め/予算重視 → MR‑P15M
- 二人暮らし/買い物頻度が多め/少し余裕のある冷蔵庫を探している → MR‑P17M
という使い分けが比較的明確です。口コミ的にも“無理なく使えている”という声が多いため、「自分の暮らしスタイルと設置環境を冷蔵庫選びにしっかり反映させる」ことが満足度を上げる鍵です。
よくある質問(Q&A形式)
Q:年間消費電力量の差が4kWh/年ですが、実際の電気代ではどれくらい違う?
A:一般家庭で1kWhあたりの電気単価が約30円と仮定すると、4kWh分で年間約120円ほどの差となります。実際には設置環境や使い方によって変わるので“大きな差”とはなりにくいですが、長く使うことを考えると無視できない部分です。
Q:高さ1,338mm/1,213mmの差はどれくらい実感する?
A:身長やキッチンの作業台高さ、上部収納棚の位置によって「上段棚に手が届きやすいか」「冷蔵庫の上に何を置けるか」が変わるため、設置前の寸法チェックが重要です。
Q:将来二人暮らしを想定していますが、最初は一人暮らし用として使えますか?
A:はい、どちらも2ドア・スリム設計なので一人暮らしでも十分に使えます。ただ、将来的に冷蔵庫の買い替えを避けたいという観点なら、MR‑P17Mの方が“少し余裕”を持って使える選択と言えます。
価格とコストパフォーマンス
MR‑P17Mの実勢価格・セール時期
MR‑P17Mの価格は「約70,642円~」という情報があります。ユーザーがショップで実際に出ている価格やセール状況をチェックすると、時期によってはさらに値下げされることもあります。冷蔵庫は家電量販店の季節セール(春の新生活、夏場の冷房関連キャンペーン、年末年始)やネットショップのタイムセールを狙うと、お得に手に入る可能性があります。
MR‑P15Mの価格推移とお買い得ポイント
MR‑P15Mの価格目安は「約60,348円~」という情報があります。容量・サイズが少し抑えめである分、価格も抑えめなので「予算を抑えつつ機能も必要十分」という選択肢として魅力的です。こちらもセール時期やポイント還元、ショップ配送・設置費用を含めて“総コスト”を確認するのがおすすめです。
電気代・長期使用コストの比較
年間消費電力量はMR‑P17Mが304kWh/年、MR‑P15Mが300kWh/年ということで、毎年の電気代差はそれほど大きくありません。しかし、10年・15年と長く使う前提なら、少しでも消費電力が低いモデルが“少しだけ安心”とも言えます。また、“部屋の温度が高め”や“開け閉め頻度が高い”といった使い方をする場合は、実消費が変わるため、容量に余裕がある方が“節電しながら使いやすい”という場面もあります。
コスパ重視ならどちらが有利?
コスパという観点では「使い方・設置環境・人数・買い物頻度」などと合わせて考えることが大切です。
- もし「一人暮らし/買い物少なめ/設置場所が狭め/価格を抑えたい」なら、MR‑P15Mがコスト的に有利。
- 逆に「少し余裕を持ちたい/二人暮らしに備えたい/買い物の頻度が多め」なら、MR‑P17Mが“容量・サイズ・機能”面で将来的に安心できる選択です。
どちらを選んでも「容量と使い方のバランス」を意識すれば、満足度の高い買い物になります。


設置・メンテナンスに関する情報
設置スペースの確保と搬入時の注意点
設置時には冷蔵庫背面や側面に“放熱スペース”が必要な場合があります。公式仕様では「据付スペース(単位:mm)」として設置条件が記載されています。搬入時には、ドア幅・廊下幅・階段の有無・エレベーターのサイズなども確認しておくと安心です。また、扉の開閉方向の影響で、壁からドアを開ける際にぶつからないか、冷蔵庫の前に家具がないかもチェックポイントです。
ドアの開き方と配置のコツ
両モデルとも「右開き」が採用されています。部屋のレイアウトを考えると、右利きの方なら冷蔵庫のドアを右側に配置することで“自然に出し入れできる”動線になります。また、上部に電子レンジや炊飯器を置く場合、フラットトップテーブル仕様(耐熱約100℃)が活かせる高さ・スペースに設置するとさらに便利です。
お手入れ・掃除のしやすさ
「棚が外して洗える」仕様なので、庫内を清潔に保ちたい方には嬉しいポイントです。また、「ガラスシェルフ」「ドアポケット可変式」「タマゴトレイ」「チューブスタンド」など、取っ手や棚の段差が少ない仕様も多いので、拭き掃除や整理整頓がラクです。冷蔵庫の扉や側面、トップテーブルも“ホコリがたまりやすい”ので、月に1度程度は拭き掃除をすることで長くキレイに使えます。
冷蔵庫を長く使うためのメンテナンス方法
冷蔵庫を長持ちさせるためには、次のポイントが大切です:
- 背面や側面に指定の放熱スペースを確保し、壁にピッタリつけず少し隙間を開ける。
- 扉ゴムパッキン(ドアを閉めたときのゴム部分)を定期的に拭き、隙間・汚れ・カビの発生を防ぐ。
- 冷凍室・冷蔵室内の食品を整理整頓して“冷気の通り道”を確保する。
- 霜取り機能が付いていても、長時間冷蔵庫を開けっぱなしにしない・庫内に熱いものを直接入れない等、運転負荷を減らす使い方を心がける。
こうした日常ケアをすることで、「購入後何年も快適に使えた」という声も多くなっています。
節電につながる使い方のコツ
- 冷蔵庫の周囲温度が高くなる夏場は、庫内温度をほんの少し上げて(例えば2~3℃)運転することで大きく消費電力が下がることがあります。
- 扉の開け閉めを頻繁にすると冷気が逃げて運転負荷が上がるため、ドアポケットや棚レイアウトを工夫して、出し入れ回数を減らすのもおすすめです。
- 食材を入れすぎて冷気の循環が悪くなると運転効率が下がるため、庫内に空間を少し残すよう意識すると良いです。
こうしたちょっとした習慣が、長期的な電気代節約&冷蔵庫寿命の延長につながります。
他シリーズ・他メーカーとの比較
三菱冷蔵庫Cシリーズ・Sシリーズとの違い
三菱電機にはPシリーズ以外にも「Cシリーズ」「Sシリーズ」などもあり、これらは容量や機能、価格帯が少し異なります。例えば“もう少し容量が大きい”モデルを探すならCシリーズ・Sシリーズが選択肢になります。Pシリーズは「スリム&使いやすさ重視」のポジションなので、用途に応じて“サイズ/価格/機能”のバランスがちょうどいい方に向いています。
同クラス他社(ハイアール・パナソニック)との比較
同容量帯・2ドア冷蔵庫として他社も多数あります。例えば、他社を比べる際には「静音性(dB)」「年間消費電力量」「設置寸法」「ドアの開きやすさ」などを基準にすると、価格だけでなく“使い勝手”で差が出やすいです。例えば「静音22dB」という仕様は、購入後に“音が気にならない”という安心感につながります。Pシリーズのこの静かさは強みと言えます。
一人暮らし向け冷蔵庫おすすめモデル紹介
もし「一人暮らし/初めて冷蔵庫を買う」という方であれば、今回紹介したMR‑P15Mはまさにおすすめ候補です。加えて、「もっとコンパクト・価格を抑えたい」という場合には容量100L前後のモデルを探すのも手です。ただし、将来二人暮らし・まとめ買いを想定するなら、最初から容量に余裕のあるモデル(今回のMR‑P17M等)を選んでおくと買い替えリスクを減らせます。


どちらを選ぶべき?タイプ別おすすめ
一人暮らし・自炊少なめならMR‑P15M
- キッチンがコンパクトで、上部収納や吊り戸棚・設置スペースに高さの制限がある。
- 自炊は軽め、買い物頻度も少なめ。
- 価格をできるだけ抑えたい。
このような条件なら、MR‑P15Mは“ちょうどいい”モデルとなります。
二人暮らし・まとめ買い派ならMR‑P17M
- 二人暮らしで、日々の買い物のまとめ買いをしたり冷蔵食品を多めにストックしたい。
- キッチンに高さの余裕があり、冷蔵庫上にレンジなどを置きたい。
- 少しだけ価格を上げても“容量のゆとり”を確保したい。
こうした場合は、MR‑P17Mを選ぶことで将来的なストレスを減らせる可能性があります。
コスパ・デザイン・静音性別おすすめモデル
- コストパフォーマンス重視 → MR‑P15M
- デザイン・容量・静音性重視 → MR‑P17M
- 静音を最優先したいなら、両モデルとも22dBという値は安心感がありますが、設置環境が“寝室隣接”か“リビング兼用”かなどでも選び方が変わります。
最終比較まとめ:あなたに合うのはどっち?
自分の暮らしを振り返って、「食材の買い出し頻度/自炊の量/設置スペースの高さ/予算/将来のライフスタイル変化(例:一人暮らし→二人暮らし)」をチェックしてみてください。
- もし「今は一人暮らしだけど将来を見据えて余裕を持ちたい」なら、MR‑P17Mも検討対象になります。
- 逆に「今の暮らしにぴったり合っていて、無駄を省いてスマートに揃えたい」なら、MR‑P15Mが最適です。
重要なのは“自分の生活スタイルに無理なくフィットする”こと。サイズが大きすぎて使いづらかったり、逆に容量が足りなくてストレスとなるのでは、せっかくの買い物が本末転倒になってしまいます。
まとめと総評
MR‑P17MとMR‑P15Mの違いまとめ
- 容量:MR‑P17Mが168L/MR‑P15Mが146L → 約22Lの差。
- 冷蔵室容量:MR‑P17Mが122L(低温ケース9L)/MR‑P15Mが100L(低温ケース9L)
- 外寸高さ:MR‑P17Mが1,338mm/MR‑P15Mが1,213mm
- 年間消費電力量:304kWh vs 300kWhとほぼ同等
- 価格目安:MR‑P17Mが約70,600円台、MR‑P15Mが約60,300円台
- 共通点として、静音22dB/幅480mm/奥行595mm/カラー2種(マットサンドブラック・マットホワイト)/2ドア右開き/間冷式(ファン式)/鋼板ドア/耐熱100℃フラットトップテーブル。
選び方のポイントをおさらい
- 設置スペースの高さ・幅・奥行きを事前に測ること。特に背面の放熱スペースを含めて余裕を。
- 「買い物頻度」「自炊頻度」「人数」を基に容量を考えること。
- 静音性やデザインも妥協せず、「毎日使う家電」にふさわしい質をチェック。
- 価格だけで選ばず、長く使えるかどうか・使いやすく感じるかどうかを重視する。
- 設置環境(搬入ルート・上部収納・運転音が響かないか)も忘れず確認。
購入前にチェックしたい注意点
- 冷蔵庫を購入する際には“搬入設置費用”や“古い冷蔵庫の処分費”も含めた総コストを考えましょう。
- キッチンの配電容量(200V/100V)・コンセント位置・床の耐荷重も確認しておくと安心。
- 実際に使ってみると、庫内の見た目や使い勝手(棚の高さ・奥行き・ドア開閉のしやすさ)で印象が変わります。可能なら実店舗で実物を確認するのがおすすめです。
- 色(マットサンドブラック/マットホワイト)もキッチンや部屋の雰囲気と合うかを検討すると、購入後の満足度が高まります。
【Amazon・楽天】最新価格をチェックする
購入を決める前には、複数の販売チャネル(Amazon、楽天、家電量販店オンラインなど)で価格比較、セール情報、送料・設置サービスの有無を必ずチェックしましょう。機種によっては販促キャンペーンやポイント還元がある場合もありますので、お得に購入できるタイミングを逃さないようにするのがおすすめです。


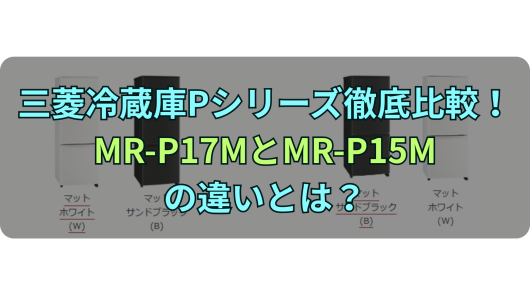
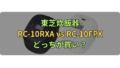

コメント